|
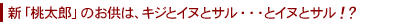 |
2009.05.15 |
|
|
|
「プロトタイプがほぼ完成したらしい」と聞いて、久しぶりにプロジェクトルームを覗くと「勉強会」の真っ最中だった。これから始まる本格的な製作を前に、サポート役をかってでてくれた後輩たちを交え、今年の競技ルールからロボットの仕様、今後のスケジュールなどの説明がつづく・・・どうやら今年は5機のロボットを製作するらしい。完成間近の試作機は3タイプ。これが新「桃太郎」たちの競技用ロボットのベースとなるようだ。
説明をおこなうのは平田さん(写真)。昨年、ロボットの製作段階から決勝戦まで、初代「桃太郎」を完全サポート。3年生ながら、今年はチームのメンバーとして競技に出場する予定だそうだが・・・進級大丈夫かなあ |
|
|
|
|
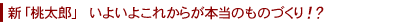 |
2009.05.28 |
|
|
|
|
|
昨年の屋根型ガレキにかわる新課題、屋根・壁・床が一体となった「家型ガレキ」。その対応策として考え出されたダミヤンの新しい救出機構の実践テストが始まっていた。
床の上のダミヤンを掬い取り、そのまま機体内部に収容する方式のようだ。
設計段階で機体前部の間口が大きく広げられ、収容スペースが確保されているように見えるが、いざテストをおこなうと、収容時にダミヤンが機体に接触してしまう「事故」が続出していた。
さて、これからどう改良していくのか?
写真は試作機を前に考え込む目さん(4年生)。「目」一字で、なんと“サッカ”と読む。いよいよ新桃太郎の「知恵」の見せどころだよね、一休さん。 |
|
|
|
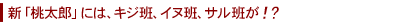 |
2009.06.04 |
|
|
|
キジ班が作成していたガレキ除去用ロボット 1号機が完成。ドでかいバンパーが印象的で、ラッセル車のようにコース上のガレキをガンガン押しのけていく勇姿が目に浮かぶ。
今年は、メンバーがキジ・イヌ・サルの3班に分かれ、それぞれが別々のロボットの設計・製作を担当する。ダミヤン救出用ロボットを製作するイヌ班はいよいよ最終段階、サル班はもうしばらく時間がかかりそうだ。
この3班のまとめ役が、“キャプテンつばさ”こと4年生の浅野さん(写真)。レスコンボードの解析からマイコンのプログラミング、ロボット設計までこなすマルチタレント。文字通りチームのキャプテンとして、今年はどんな「チーム桃太郎」を作り上げてくれるだろう。 |
|
|
|
|
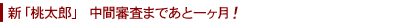 |
2009.06.08 |
|
|
|
|
|
予選まで一ヶ月を切った。どうやら今年は昨年のような「予選競技」はおこなわれないそうだ。代わりに、ロボットのパフォーマンスを撮影したビデオを用いたプレゼンテーションがおこなわれ、その審査によって本選出場チームが絞り込まれるらしい。
少々拍子抜けの感もあるが、プレゼン資料を制作するには、ロボットはもちろん、操縦技術も完成させておかなければ・・・ロボット製作と平行して、学内某所ではサポート役の後輩たちによって練習用のコース作りも着々と進められているようだ。
写真は1号機を完成させ、早速共通部品の製作に取り掛かるキジ班の吉田さん(4年生)。新桃太郎のマイスターは、これからチームの「危機」を何度も救ってくれることだろう。 |
|
|
|
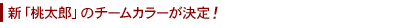 |
2009.06.10 |
|
|
|
新桃太郎のチームカラーが決まった。
アクリル製で今は透明なロボットのボディもまもなくチームカラーに統一されるはず。7月5日におこなわれる中間審査をクリアできれば、8月の神戸で、今年は、「ワインレッド」にカラーリングされたロボットたちの「円舞」を楽しむことができる。
写真は、1号機のガレキ除去バンパーの取付位置を微調整するためにパーツにヤスリをかけるキジ班の上枝さん(4年生)。1号機の操縦を担当する予定。ふだんは穏やかな性格の上枝さんだが、本番では豹変して、ド派手なパフォーマンスを披露してくれるかも・・・ |
|
|
|
|
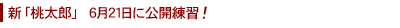 |
2009.06.10 |
|
|
|
|
|
「今日は用があるのでお先に」と部屋を出ていったサル班の島田さんだったが、また4号機を前に腰を落ち着けてしまった。どうやら製作を担当する、ロボットハンドを懸架するクレーンの強度が気になったようだ。(写真)
ダミヤンの救出には、新規に考案した「救出用ベッド」が用いられる予定だが、ロボットハンドも補助用として、4機の救出用ロボットの上部に搭載される。
ロボットハンドは目下、目さんが考案中。これが最後のメインパーツとなる。
ところで、6月21日に開催されるオープンキャンパスでロボットのデモをおこなうらしい・・・公開練習といえば、昨年、クレーンのアーム部がボキリと破断する「事故」があったのを思い出すが、今年は大丈夫のようだ。 |
|
|
|
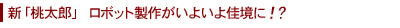 |
2009.06.12 |
|
|
|
「ナンデヤ!」・・・プロジェクトルームにキジ班の吉田さんの声が響き渡った。やっとの思いで1号機のすべての配線を終え、バッテリーをつないだ瞬間、ロボットが暴走した。原因を突き止めるには、また・・・。
ロボットには、モータや制御基盤、カメラなどのさまざまな電子部品とこれらすべてを制御するレスコンボードが搭載されていく。それらをつなぐ配線がまるで血管のように見えてきて・・・ロボットに「いのち」が宿っていく感じ。
写真は、4号機の配線に取り掛かったサル班の中島(ナカシマ)さん。なかなか部品が届かず、家ネコのように“まったり”と時間をやり過ごしていたが、今日は獲物を追い詰める野生のイメージかな? |
|
|
|
|
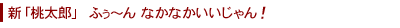 |
2009.06.12 |
|
|
|
|
|
今年も、「最近寝てないんですう」がすっかり口癖になってしまった桃太郎の育て親の赤木先生。県北から1時間半をかけて通勤。帰りはほとんど最終電車ということだから、「寝る時間がない」のは容易に想像できるのだが・・・なんだか挨拶の言葉ぐらいにしか聞こえてこなくなったなあ・・・。
それにしてもタフな先生だ。このところの順調な進捗状況に一安心といった表情を浮かべながら、各班の作業を見回っては、短くアドバイスを送る。
写真は、改良した救出用アームを使って、家型ガレキからダミヤンを救出する2号機の様子を楽しそうに見守る赤木先生。桃太郎たちの成長が、きっとこの先生にとってのキビダンゴなんだろうなあ |
|
|
|
 |
2009.06.17 |
|
|
|
| アクリル板からロボットのパーツを削り出すには小型のレーザー加工機が使用されるのだが、今年の桃太郎はウォータージェット加工機まで使いこなす。水の力で携帯電話も一瞬で「まッ二つ」ってやつだ。写真は、テスト中に破損した部品を作りにやってきた浅野さんと目さん。データを入力し、アクリル板をセット。あっという間に作業は完了した。 |
|
|
|
|
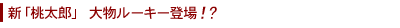 |
2009.06.17 |
|
|
|
|
|
「このチームに参加したくてこの学科に入ったんですよ」と、なかなか嬉しいことを言ってくれるのがサル班の福井さん。昨年の夏の神戸で、初代桃太郎の活躍を目の当たりにして一念発起、この春、高専から入学してきたばかりだが、その「腕」を見込まれ、4号機の救出用アームの製作を任された。
講義の合間を利用しながらようやく完成させたアームは、さすが、スマートに仕上っているのだが、本人はまだまだ納得のいくデキではない様子。
写真は、「もう一度作り直しですよ」と、照れながらアームを取り付けて見せてくれる福井さん。長い髪を後ろで束ねたその風貌は、幕末の「龍馬」を想わせる・・・この男、ただ者ではないな。 |
|
|
|
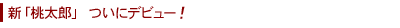 |
2009.06.21 |
|
|
|
オープンキャンパスに来た高校生たちを前に、新桃太郎がデビューを飾った。初練習がデビュー戦とあって、「華々しい」とはいかなかったが、メンバーたちは一様に「手ごたえ」を感じたようだ。
写真は、ロボットに搭載したカメラからの映像を頼りに1号機を操縦する上枝さんと2号機を操縦する目さん。「緊張しました」が上枝さんの第一声。 |
|
|
|
|
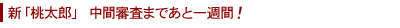 |
2009.06.27 |
|
|
|
|
|
サル班の島田さんと中島さんのシマシマコンビが、ようやく完成した4号機のロボットハンドの位置調整をおこなっている(写真)。うまくダミヤンを救出できる場所がなかなか見つからないようだ。時折、接触不良かどこかでノイズでも発生しているのか、ロボットが操縦不能に陥る。完璧に仕上るまでにはもう少し時間がかかりそうだ。
中間審査まで残すところあと一週間となった。焦りと諦めと睡眠不足にさいなまれる一週間だが、絶妙なチームワークを作り出すためには、欠かせない熟成期間となるハズ。 |
|
|
|
|
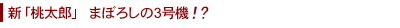 |
2009.07.02 |
|
|
|
まぼろしの3号機がようやくその姿を現し始めた。3号機は2号機のサブ機でほぼ同じ仕様だが、ダミヤンを収容する移動式ベッドの駆動方法が異なる。(下)
製作を担当するのは、チーム唯一の3年生の平田さん(右)。「授業最優先」がチーム参加の絶対条件となっているだけに、空き時間を見つけてはコツコツと作業を続けている。 |
|
|
| ウレタンローラー(3号機) |
|
マジックハンド(2号機) |
|
|
|
|
|
|
|
|
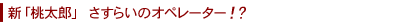 |
2009.07.02 |
|
|
|
いづれの班にも属さず、各班のサポートに徹してきた「さすらいのメンバー」こと4年生の岡村さんが2号機のオペレーターに大抜擢された。
この日も、5日におこなわれるテストランに向け猛特訓にあたっていたが、ロボットハンドを使って大ダミヤンを持ち上げようとした瞬間、鈍い音がプロジェクトルームにこだました。
クレーン部とボディーをつなぐアクリル製のジョイント部が破断してしまったようだ。早速、4号機と同じ金属製の仕様に変更されることになったが・・・。
写真は、「音」の発生源を確認する岡村さん。さすらいのオペレーターも、ダミヤンの「恐ろしさ」をじんわりと感じ始めたようだ。 |
|
|
|
|
 |
2009.07.02 |
|
|
|
「先生 ここが気になるんです・・・」
「そこ・・・矢印つければいいんじゃない」
写真は、講義の合間に様子を見に来た赤木先生にアドバイスを求めるキャプテン翼さん。中間審査会でチーム「桃太郎」のプレゼンテーターを務める。時間を計りながら練習を繰り返しては、プレゼン用資料に修正を加えていく。
5日の審査会では、ロボットのパフォーマンスを撮影した映像を交えながら、チームのコンセプトやロボットの機能を紹介する。持ち時間は7分間。これをオーバーすると減点になるらしい。 |
|
|
|
|
|
|
 |
2009.07.05 |
|
|
|
|
|
「エッ! 審査員席ってこんなに近いの」
7月5日(日)、午前10時30分、メンバーたちが見守る中、チーム「桃太郎」のプレゼンテーションが始まった。プレゼンテーターはキャプテン翼さん。目の前に陣取る5人の審査委員に、さすがのキャプテンも、出だしで危うく声がひっくり返りそうになったが、すぐにいつもの渋い声を取り戻した。
写真は、発表後の質疑応答で審査員からの鋭い(?)質問にも動じることなく対応する翼さん。チームのコンセプトもロボットのパフォーマンスも、しっかり審査員に理解してもらえたようだ。
結果は20チーム中第8位。まずまずの成績で中間審査をクリアーした。 |
|
|
|
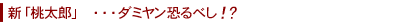 |
2009.07.09 |
|
|
|
「5日のテストランはどうだったの」とのお尋ねがあったのでご紹介しましょう。
テストランは実際の競技フィールドの1部を使っておこなわれた公開練習で、チーム「桃太郎」の持ち時間は午後1時30分からの30分間。出番を待つメンバーたちは終始余裕の表情を見せていたが、いざ本番が始まると、「実物」のダミヤン相手に悪戦苦闘。さらに空気漏れに、コントローラーの誤動作と思わぬトラブルが発生、メンバーの顔から表情が消えていく・・・。なんとか1体のダミヤンを救出することに成功したのだが、自信をもって臨んだメンバーたちにとっては、課題山積のほろ苦いテストランだったようだ。
|
|
 テストランの様子はこちら テストランの様子はこちら |
|
|
|
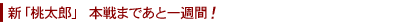 |
2009.08.02 |
|
|
|
|
|
夏のオープンキャンパスで知能機械工学科の学科イベントに久し振りにチーム「桃太郎」が登場した。この1ヶ月間でテストランでの問題点はほぼ解消したようで、見学に来た高校生たちを前に完璧なパフォーマンスを披露した。
この日操縦を担当した上枝さん、キャプテン翼さん、島田さんの背中も自信たっぷりといった感じで、あとは本番を待つばかりの状態だ。
8月8日のファーストミッションでは、上位4チームが無条件にファイナルミッション(9日午後)に進出、残る上位6チームによってファイナル進出をかけたセカンドミッション(9日午前)がおこなわれる。 |
|
|
|
 |
2009.08.07 |
|
|
|
8月7日午前7時、桃太郎たちが神戸へと出発していった。7日にはロボットの「車検」と競技フィールドでのテストランがおこなわれる。この1週間、練習を続けてきた「トラの穴」からはロボットが消え、ホワイトボードのカウントダウンに「今日出発!」の文字だけが残る。
さて、今年のチームはどんなパフォーマンスを見せてくれるだろう。「やさしくダミヤンを救出」という「桃太郎」のコンセプトをどこまで実践してくれるだろう。
写真は、ようやく「まぼろし」ではなくなった3号機の最終調整をおこなう平田さん。「本番までには・・・」の言葉通り、なんとか間に合ったね、平田さん。
(8月6日撮影/製作終了) |
|
|
|
|
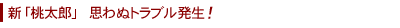 |
2009.08.08 |
|
|
|
|
|
ファーストミッション第5競技。順調な滑り出しをみせた「桃太郎」だったが、救出を開始した途端、次々にロボットが停止してしまった。何が起こったのか分からず慌てるメンバーたち。どうやら通信障害のようだ。フィールドのロボットは止まったまま、時間だけが過ぎてゆく・・・
仕方なく「リスタート」を申請し、一機ずつ回収。再開後ようやく一体目のダミヤンを救助。家ガレキのダミヤンを収容したところで、無情にも「競技終了」。
ロボットを完璧に仕上げて競技に臨んだだけにメンバーたちの悔しさはひとしお。桃太郎たちの夏は、「何もしないまま」 あっけなく終わってしまった。
|
 競技の様子はこちら 競技の様子はこちら |
|
|
|
|
|
 |
|